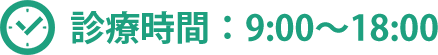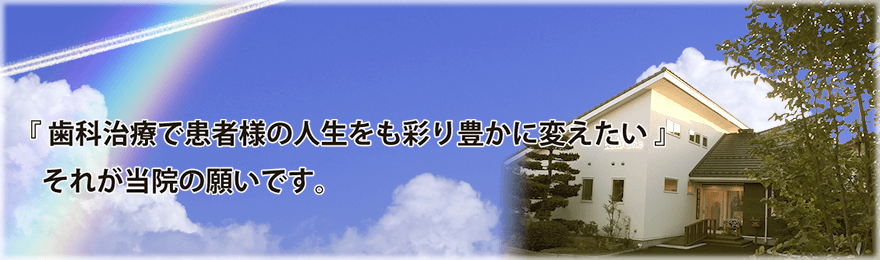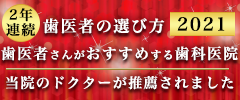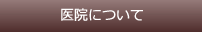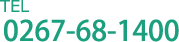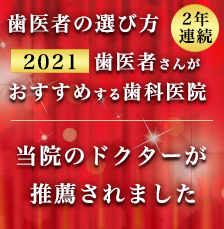歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)
歯初診とは、歯科医院における院内感染防止を推進するための基準の一つです。 以下の条件を満たすと施設基準として認定されます。
(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等において、専用機器にて洗浄・滅菌、患者様毎での交換等、院内感染対策を徹底していること。
(2) 感染症患者に対する歯科診療体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師1名以上が配置されていること。
(4) 職員を対象とした院内感染防止対策において、標準予防策及び新興感染症に対する対策等の研修等を行っていること。
(5) 院内感染防止対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
(6) 院内感染対策の実施状況等について、年に1回、地方厚生(支) 局長に報告していること。
歯科外来診療医療安全対策加算1
歯科外来診療医療安全対策加算とは、必要な機器の保有や他の医療機関との連携等を通して、医療事故を未然に防ぐための体勢が整っているかどうかを評価する基準です。 以下の条件を満たすと施設基準として認定されます。
(1) 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く) であること。感染症患者に対する歯科診療体制を確保していること。
(2) 歯科点数表の初診料の注1に係る施設基準の届出を行っていること。
(3) 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4) 歯科衛生士が1名以上配置されていること。
(5) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED) については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(1) 自動体外式除細動器(AED)
(2) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(3) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(4) 血圧計
(5) 救急蘇生セット
(6) 歯科用吸引装置
(6) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りでない。
(7) 歯科用吸引装置等により、歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できる環境を確保していること。
(8) 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
歯科外来診療感染対策加算1
歯科外来診療感染対策加算とは、治療時の偶発症などの緊急時の対応及び感染症対策としての装置・器具の設置など、総合的な歯科医療環境が整っているかどうかを判断する基準です。 以下の条件を満たすと施設基準として認定されます。
(1) 歯科医療を担当する保険医療機関(歯科点数表の地域歯科診療支援病院歯科初診料にかかる施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を除く) であること。
(2) 偶発症に対する緊急時の対応、医療事故対策等の医療安全対策に係る研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(3) 歯科医師が複数名配置されていること、または歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(4) 医療安全管理者が配置されていること。ただし、病院である医科歯科併設の保険医療機関(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関をいう。以下同じ) にあっては、歯科の外来診療部門に医療安全管理者が配置されていること。
(5) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。また、自動体外式除細動器(AED) については保有していることがわかる院内掲示を行っていること。
(1) 自動体外式除細動器(AED)
(2) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(3) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(4) 血圧計
(5) 救急蘇生セット
(6) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の保険医療機関にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
(7) 以下のいずれかを満たしていること。
(1) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(2) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
(8) 当該保険医療機関の見やすい場所に、緊急時における連携保険医療機関との連携方法やその対応等、歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
(9) (8) の掲示事項について、原則としてウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
歯科治療総合医療管理料
十分な経験を有する常勤の歯科医師、歯科衛生士などにより、治療前や治療中および治療後の患者様の全身状態を管理できる体制が整備されているかを判断するための基準です。高血圧や糖尿病などの病気を抱えている方には、全身状態の管理や血圧や脈拍、酸素飽和度などを測定しながら治療をしていきます。
口腔管理体制強化加算
口管強とは、むし歯や歯周病の予防を目的とし、地域の皆様のお口の健康をお守りするための、地域完結型医療推進を担う歯科医療機関のことです。 以下の条件を満たすと施設基準として認定されます。
(1) 歯科医師が複数名配置されていること又は歯科医師及び歯科衛生士がそれぞれ1名以上配置されていること。
(2) 以下のいずれにも該当すること。
(1) 過去1年間に歯周病安定期治療又は歯周病重症化予防治療をあわせて30回以上算定していること。
(2) 過去1年間にエナメル質初期う蝕管理料又は根面う蝕管理料をあわせて12回以上算定していること。
(3) 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準を届け出ていること。
(4) 歯科訪問診療料の注15に規定する届出を行っていること。
(3) 過去1年間に歯科疾患管理料(口腔機能発達不全症又は口腔機能低下症の管理を行う場合に限る) 、歯科衛生実地指料口腔機能指導加算、小児口腔機能管理料、口腔機能管理料又は歯科口腔リハビリテーション料3をあわせて12回以上算定していること。
(4) 以下のいずれかに該当すること。
(1) 公益財団法人日本医療機能評価機構が行う、歯科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録することにより、継続的に医療安全対策等に係る情報収集を行っていること。
(2) 歯科外来診療において発生した医療事故、インシデント等を報告・分析し、その改善を実施する体制を整備していること。
(5) 過去1年間の診療情報提供料又は診療情報等連携共有料があわせて5回以上算定している実績があること。
(6) 当該医療機関に、歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること) 、高齢者並びに小児の心身の特性及び緊急時対応に関する適切な研修を修了した歯科医師が1名以上在籍していること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
(7) 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること。ただし、医科歯科併設の診療所にあっては、当該保険医療機関の医科診療科との連携体制が確保されている場合は、この限りではない。
(8) 当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
(9) (5) に掲げる歯科医師が、以下の項目のうち、3つ以上に該当すること。
(1) 過去1年間に、居宅療養管理指導を提供した実績があること。
(2) 地域ケア会議に年1回以上出席していること。
(3) 介護認定審査会の委員の経験を有すること。
(4) 年1回以上、在宅医療に関するサービス担当者会議や病院・診療所・介護保険施設等が開催する多職種連携に係る会議等に年1回以上出席していること。
(5) 過去1年間に、在宅歯科栄養サポートチーム等連携指導料を算定した実績があること。
(6) 在宅医療又は介護に関する研修を受講していること。
(7) 過去1年間に、退院時共同指導料1、在宅歯科医療連携加算1、在宅歯科医療連携加算2、在宅歯科医療情報連携加算、小児在宅歯科医療連携加算1、小児在宅歯科医療連携加算2、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料を算定した実績があること。
(8) 認知症対応力向上研修等、認知症に関する研修を受講していること。
(9) 過去1年間に福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、介護老人福祉施設又は介護老人保健施設における定期的な歯科健診に協力していること。
(10) 自治体が実施する事業(ケに該当するものを除く) に協力していること。
(11) 学校歯科医等に就任していること。
(12) 過去1年間に、歯科診療特別対応加算1、歯科診療特別対応加算2又は歯科診療特別対応加算3を算定した実績があること。
(10) 歯科用吸引装置により、歯科ユニット毎に歯の切削や義歯の調整、歯冠補綴物の調整時等に飛散する細やかな物質を吸引できる環境を確保していること。
(11) 患者にとって安心で安全な歯科医療環境の提供を行うにつき次の十分な装置・器具等を有していること。自動体外式除細動器(AED)
(1) 自動体外式除細動器(AED)
(2) 経皮的動脈血酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)
(3) 酸素(人工呼吸・酸素吸入用のもの)
(4) 血圧計
(5) 救急蘇生セット
(6) 歯科用吸引装置
なお、自動体外式除細動器(AED) については保有していることがわかる院内掲示を行っていることが望ましい。
在宅療養支援歯科診療所1
過去1年間に歯科訪問診療料1及び歯科訪問診療2を合計15回以上算定していること。
高齢者の心身の特性(認知症に関する内容を含むものであること。)、口腔機能の管理、緊急時対応等に係る適切な研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。なお、既に受講した研修が要件の一部を満たしている場合には、不足する要件を補足する研修を受講することでも差し支えない。
歯科衛生士が配置されていること。
当該診療所において、歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な保険医をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。
歯科訪問診療に係る後方支援の機能を有する別の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
当該診療所において、過去1年間の在宅医療を担う他の保険医療機関、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所又は介護保険施設等からの依頼による歯科訪問診療料の算定実績が5回以上であること。
在宅療養支援歯科診療所1の場合は、以下のいずれか1つに該当すること。
当該地域において、地域ケア会議、在宅医療・介護に関するサービス担当者
1.会議又は病院・介護保険施設等で実施される多職種連携に係る会議に年1回以上出席していること。
2.過去1年間に、病院・介護保険施設等の職員への口腔管理に関する技術的助言や研修等の実施又は口腔管理への協力を行っていること。
3.歯科訪問診療に関する他の歯科医療機関との連携実績が年1回以上あること。
在宅療養支援歯科診療所1の場合は、過去1年間に、以下のいずれかの算定が1つ以上あること。
1.栄養サポートチーム等連携加算1又は2の算定があること。
2.在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料の算定があること。
3.退院時共同指導料1、退院前在宅療養指導管理料、在宅患者連携指導料又は在宅患者緊急時等カンファレンス料の算定があること。
直近1か月に歯科訪問診療及び外来で歯科診療を行った患者のうち、歯科訪問診療を行った患者数の割合が9割5分以上の診療所にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
1.過去1年間に、5か所以上の保険医療機関から初診患者の診療情報提供を受けていること。
2.直近3か月に当該診療所で行われた歯科訪問診療のうち、6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
3.在宅歯科医療に係る3年以上の経験を有する歯科医師が勤務していること。
4.歯科用ポータブルユニット、歯科用ポータブルバキューム及び歯科用ポータブルレントゲンを有していること。
5.歯科訪問診療において、過去1年間の診療実績(歯科点数表に掲げる区分番号のうち、次に掲げるものの算定実績をいう。)が次の要件のいずれにも該当していること。
a. 区分番号「I005」に掲げる抜髄及び区分番号「I006」に掲げる感染根管処置の算定実績が合わせて20回以上であること。
b. 区分番号「J000」に掲げる抜歯手術の算定実績が20 回以上であること。
c. 区分番号「M018」に掲げる有床義歯を新製した回数、区分番号「M029」に掲げる有床義歯修理及び区分番号「M030」に掲げる有床義歯内面適合法の算定実績が合わせて40 回以上であること。ただし、それぞれの算定実績は5回以上であること。
・年に1回、歯科訪問診療の患者数等を別添2の様式18 の2を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
在宅患者歯科治療総合医療管理料
在宅患者歯科治療時医療管理料は、在宅療養を行う患者様に対して、歯科医師が計画的な診療管理を行った場合に算定される報酬です。以下の条件を満たすと施設基準として認定されます。
(1) 患者の状態に基づいて口腔管理や治療計画を策定し、それを患者またはその家族に説明・提供すること。
(2) 診療計画には、治療の目標、管理内容、訪問スケジュールなどを明記すること。
(3) 患者の口腔内の健康状態を定期的にチェックし、適切なケア(歯石除去、清掃指導、義歯の調整など) を行うこと。
(4) 必要に応じて、診療計画を見直し、変更した内容を記録すること。
(5) 診療内容、患者の健康状態、対応したケアについて記録し、一定期間保存すること。
(6) 実際に患者の自宅や施設を訪問し、診療を行った場合に算定可能。
(7) 診療計画や訪問診療の内容について患者またはその家族から同意を得ること。
(8) 他の医療機関や介護サービス事業者と連携し、全身管理が必要な場合は適切な医療提供を確保すること。
地域医療連携体制加算
地域医療連携体制加算とは、障がい福祉サービス事業所と医療機関等が連携して、障がい者や障がい児に対して看護や喀痰吸引等の指導を行う場合に算定される加算です。以下の条件を満たすと施設基準として認定されます。
(1) 地域の他の医療機関(特に、病院や他の歯科医院など) や介護施設(特別養護老人ホーム、訪問看護ステーションなど) と連携体制を構築していること。
(2) 自院が地域における医療の一環として機能していること。
(3) 紹介患者の受け入れ、または紹介患者の他施設への送付が適切に行われていること。
(4) 診療情報提供書や報告書を交付するなど、診療情報のやり取りが継続的に行われていること。
(5) 医療連携に関する研修を定期的に実施し、医師、歯科医師、スタッフが地域医療についての理解を深めていること。
(6) 地域医療連携に関する取り組みの具体的内容を記載した書面が作成され、保険者などに報告可能な状態で保管されていること。
(7) 地域医療連携の方針について、患者やその家族に説明し、必要に応じて同意を得ること。
手術用顕微鏡加算
根管治療でマイクロスコープを使用する際、下記の条件を満たした時に、保険で算定することができます。
(1) 手術用顕微鏡(マイクロスコープ) を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 院内に手術用顕微鏡が設置されていること。
CAD/CAM冠施設設置基準
CAD/CAM冠とは、セラミックと歯科用レジンを合わせた素材の白い被せ物です。下記の条件を満たした時に、保険で算定することができます。
(1) 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 院内に歯科技工士が配置されていること、または歯科技工所と連携が図られていること。
(3) 院内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていること、または当該装置を設置している歯科技工所と連携が図られていること。
歯根端切除手術の注3
根管治療を続けても完治が難しい場合は抜歯の選択肢がありますが、抜歯せずに歯を残す治療法が歯根端切除手術です。下記の条件を満たした時に、保険で算定することができます。
(1) 手術用顕微鏡(マイクロスコープ) を用いた治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 院内に手術用顕微鏡が設置されていること。
クラウン・ブリッジ維持管理料
保険でクラウン・ブリッジを装着した日から2年以内に新しく作製し直す場合、その部位の検査費・作製費・装着費は無料になります。この届け出をしていない場合は、これらの保証は適応されませんが、当院では保証されています。
※初診料やその他の治療費は除きます。
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
医療従事者の人材確保や賃上げに向けた取り組みの一つとして、「ベースアップ評価料」が新設されました。下記の基準を満たした場合には、賃上げ促進税制の対象となり、増加額の一部を税額控除することが可能となります。
(1) 外来医療または在宅医療を実施している保険医療機関であること。
(2) 主として歯科医療に従事する職員(医師及び歯科医師を除く。以下、この項において「対象職員」という)が勤務していること。対象職員は専ら事務作業(歯科業務補助者等の歯科医療を専門とする職員の補助として行う事務作業を除く)を行うものは含まれない。
(3) 当該評価料を算定する場合は、令和6年度及び令和7年度において対象職員の賃金(役員報酬を除く)の改善(定期昇給によるものを除く)を実施しなければならない。
(4) (3) について、ベア等により改善を図るため、当該評価料は、対象職員のベア等及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む)等の増加分に用いること。ただし、ベア等を行った保険医療機関において、患者数等の変動等により当該評価料による収入が上記の増加分に用いた額を上回り、追加でベア等を行うことが困難な場合であって、賞与等の手当によって賃金の改善を行った場合、または令和6年度及び令和7年度において翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合(令和8年12月までに賃金の改善措置を行う場合に限る)についてはこの限りではない。いずれの場合においても、賃金の改善の対象とする項目を特定して行うこと。なお、当該評価料によって賃金の改善を実施する項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く)の水準を低下させてはならない。また、賃金の改善は、当該保険医療機関における「当該評価料による賃金の改善措置が実施されなかった場合の賃金総額」と、「当該評価料による賃金の改善措置が実施された場合の賃金総額」との差分により判断すること。
(5) 令和6年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して2分5厘以上引き上げ、令和7年度に対象職員の基本給等を令和5年度と比較して4分5厘以上引き上げた場合については、40歳未満の勤務歯科医及び勤務医並びに事務職員等の当該保険医療機関に勤務する職員の賃金(役員報酬を除く)の改善(定期昇給によるものを除く)を実績に含めることができること。
(6) 令和6年度及び令和7年度における当該保険医療機関に勤務する職員の賃金の改善に係る計画(以下「賃金改善計画書」という)を作成していること。
(7) 当該保険医療機関は、当該評価料の趣旨を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。
(8) 当該保険医療機関は、対象職員に対して、賃金改善を実施する方法等について、2の届出に当たり作成する「賃金改善計画書」の内容を用いて周知するとともに、就業規則等の内容についても周知すること。また、対象職員から当該評価料に係る賃金改善に関する照会を受けた場合には、当該対象者についての賃金改善の内容について、書面を用いて説明すること等により分かりやすく回答すること。